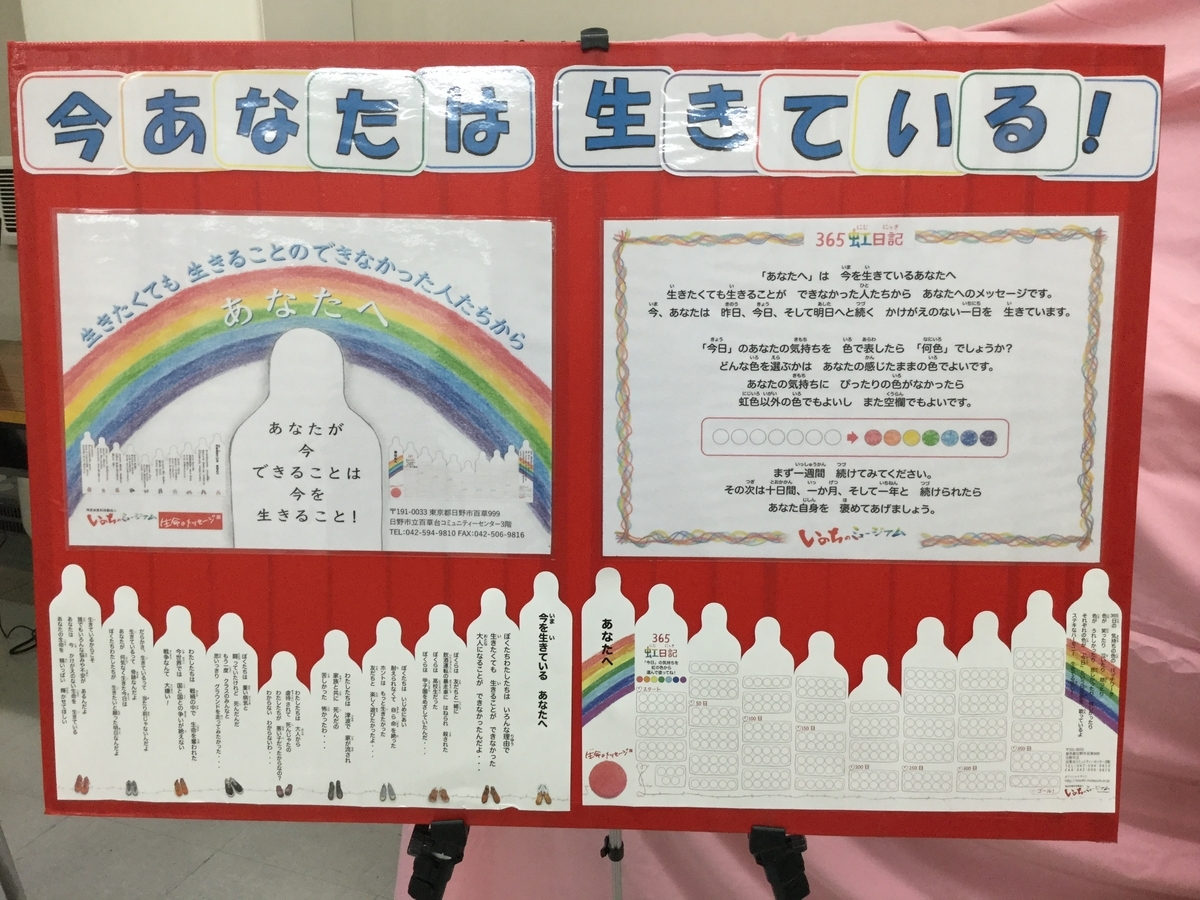前回のブログでは2023年の振り返りを行った。それを受けて、未来に何が起きるか想定して、自分に係ることを中心に時代に合った対応(行動)をしていくことが必要だと感じている。
充実した人生を過ごすには、身体健康(生命)、世界平和、愛情・互助・人脈(人との緩いつながり)、サムマネーが大切だと痛感しているので、元旦に地元神社での初詣で、今より向上するよう祈願した。
これからの人生100年時代、所得を増やすには、現役で働く総時間(期間)を増やす必要がある。時間を味方につけるには、長期間働ける健康時間を増やすことが必要不可欠。
栄養のある食事(朝食をしっかりとる)、適度な運動(日々のラジオ体操、1日8000歩以上など)、休養(翌日に就寝しない、夜深ししない)、虫歯予防(食後に歯を丁寧に磨く)は毎日のことなので、持続可能な生活習慣となるよう意識して取り組んでいく。
2024年の想定
1月 新NISA開始、台湾総統選挙
人生100年時代には時間を味方につけることが不可欠。日経平均株価は、浮沈を繰り返しながらスパイラルアップしている。
物価も同様であり、人類は、これから初体験すること(人口減少、少子高齢化など)でも、イノベーションなどで適応していくと思われる。
地球が滅亡しない限り、経済は成長していく。とすると、新NISAでの投資信託などで時間を味方につけて長期積み立て投資をすることは有効なサムマネー対策となる。(自己責任であり、生活の余剰資金で行うことは重要。投機(ばくち)ではなく、投資であることを忘れずに!)
選挙の結果、与党民進党が野党国民党か、それとも第3勢力が政権を担うのか。台湾と中国の今後の関係がどうなるか、地政学的に日本の安全保障に大きくかかわる今後の政局運営に注目が集まる。
2月 春闘
引き続き大幅な賃上げができるかが、デフレ脱却の鍵。
持続可能な経済活動(デフレ脱却)をするには、物価高に合わせた実質賃金の上昇が不可欠。
中小企業が賃上げに耐えられるだけの経営ができるか、それをサポートするために政府の補助金などでサポートしつつ、経営改革や技術革新などで持続可能な企業経営を進めるか。それでも経営が厳しければ市場からの撤退、合併なども含め考えていく必要がある。
持続可能な経済の成長の阻害要因として、戦争が挙げられる。一刻も早い停戦とこれから戦争が起きないよう国連改革なども急務だと考える。
5大国(戦勝国)の特権(拒否権)をなくし、安全保障理事会の機能を強化するなど加盟国が一丸となって本気で取り組む必要がある。
国内交通インフラが進むことで、経済にも大きな恩恵をもたらす。人の異動(ビジネス・観光)、物資の異動で地域の活性化ももたらす。北陸新幹線京都までの延伸、リニアモーターカー、北海道新幹線の札幌までの延伸(オリンピック・パラリンピック開催まで難しいか?)など日本の主要都市を結ぶ交通基盤の発達は、日本経済の活性化につながると思う。
また、日本経済のデフレ脱却の鍵は、春闘での賃上げの動向を見極めながら、マイナス金利解除に動くかどうか。賃上げの成功が政権の命綱になるかもしれない。
4月 2024年問題
建設業、運輸業、医療の認められていた時間外の上限規制の猶予(年間960時間)がなくなる。
安全が担保されることが大前提で、賃上げや業界規制緩和やイノベーションなどで乗り切っていく必要がある。
自動運転、ドローン、シェアライド、在宅勤務の普及、医療介護ロボット、通訳機器など・・。
*国主催の情報通信審議会が、2030年代に実現したい未来の姿の実現に向けた行程イメージを参考。
6月 所得税減税開始
2023年度予算の国の一般会計歳出は、114.4兆円で、主に社会保障(年金、医療、介護、こども・子育て等のための支出)、国債費(国債の償還(国の借金の元本の返済)と利払いを行うための経費)、地方交付税交付金等(どこでも一定のサービス水準が維持されるよう、国が調整して地方団体に配分する経費)に使われており、これらで2/3を上回っている。
国の歳入は、税収等と公債金(借金)で構成され、税収等(所得税、法人税、消費税等の税による収入とその他の収入)では歳出全体の約2/3しか賄えておらず、残りの約1/3は公債金(歳入の不足分を賄うため、国債(借金)により調達される収入)に依存しており、この借金の返済に将来世代の税収等が充てられるため、将来世代へ負担を先送りしていることになる。
これから当分の間、少子高齢社会続く中、短期的な政策だけでなく、国がいくつかのシナリオを作成し、中長期的な展望とそれに対する対策案を示して、国政選挙において重要な争点にして国民的な議論にしていく機運を高めていく時期に来ていると思う。
将来、高福祉社会あるいは中福祉社会を目指すのか、それによって国税、地方税の住民の税負担のあり方(各税制度の応能負担、応益負担など)を見直すとともに、税金の使われ方の情報公開を徹底し、透明化を図ることが必要だと考える。
具体的には、子育て世代の支援として、学生時代までの医療費無償化、給食費等の無償化、高校、大学授業料の無償化など、どこまで国が責任をもっておこなうか。もしこれらを実施する場合は、持続可能な財源をどう生み出すか、党利党略ではなく、国民のために国会で徹底的に議論してもらいたい。
7月 東京都知事選挙
新紙幣発行(1万円:渋沢栄一、5千円:津田梅子 千円:北里柴三郎)
自動販売機等などの需要増など特需、紙幣の切り替えでタンス預金が減り、キャッシュス化も進むことが想定される。
8月 パリオリンピック・パラリンピック開催
技術革新によりユニバーサルデザイン化が進み、自動翻訳機など2025年開催のデフリンピックにも好影響を与えると思う。
9月 自民党総裁任期
支持率低迷の中、参議院議員選挙を戦えるのかも含め、自民党の顔としての総裁選挙は注目される。
11月 アメリカ大統領選挙
共和党のトランプVS民主党のバイデンの一騎打ちか。どちらが大統領になっても健康不安はぬぐえない。ロシア、中国、イスラエルの関係など国際情勢にも変化が出る可能性もある。日本の安全保障や貿易にもにもかかわってくることが想定される。
12月 熊本で台湾半導体TSMCが工場稼働
半導体の製造工場が国内で誘致されている。雇用の創出、世界の半導体競争に勝つためにも国内企業のイノベーションにも期待。
番外編
生成AI
ジェネレーティブAIともいわれ、多様なコンテンツを作成できる人工知能の一種。主に4種類に分類されており、「画像生成」「テキスト生成」「動画生成」「音声生成」などそれぞれの特徴に応じた用途に活用されている。大量のデータに基づく特徴や傾向の学習によって成否の判別や予測を行うために活用する従来のAIと異なる。
生成AIの一種であるチャットGPTは、人間のように自然な会話ができるAIチャットサービスで、生成した文章の完成度が高く人間味のある回答をする。
- 主なメリットは、業務効率化、アイデアの提案、コスト削減が可能となるが、使い方を間違えると犯罪などへの悪用(個人情報の漏洩など)、著作権問題、クリエイターの雇用や収入の減少などの問題もはらんでいる。
- 技術革新によって生活の向上など利便性の向上につながる一方、運用ルールやセキュリティー対策などを万全にしないと、クローン技術、原子力開発などと同様、取り返しがつかないことになりかねないのでリスクを十分把握したうえで適切に活用していくことが重要だと思う。
-
(参考)未来年表
- NRI未来年表 2024-2100 | 野村総合研究所(NRI)
- 未来年表 | 生活総研